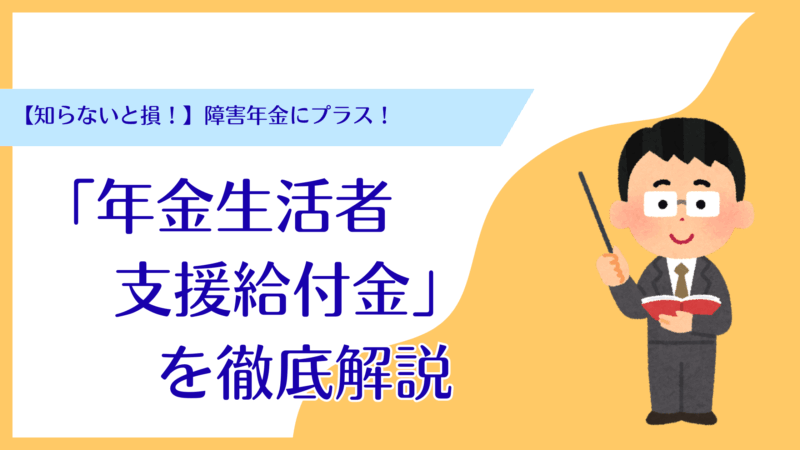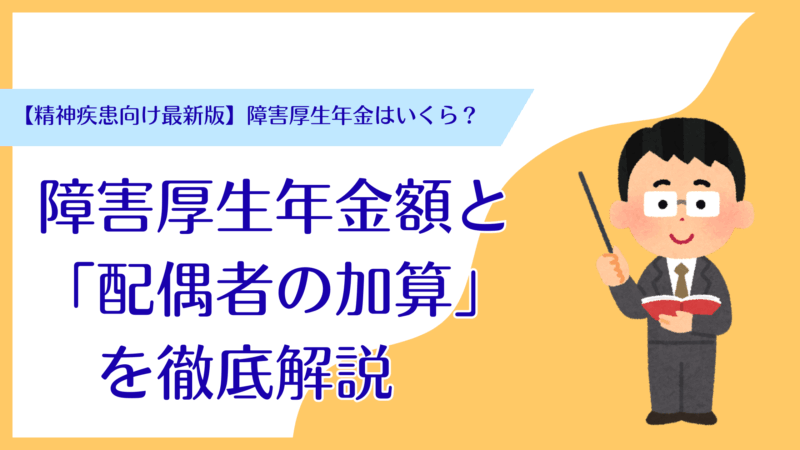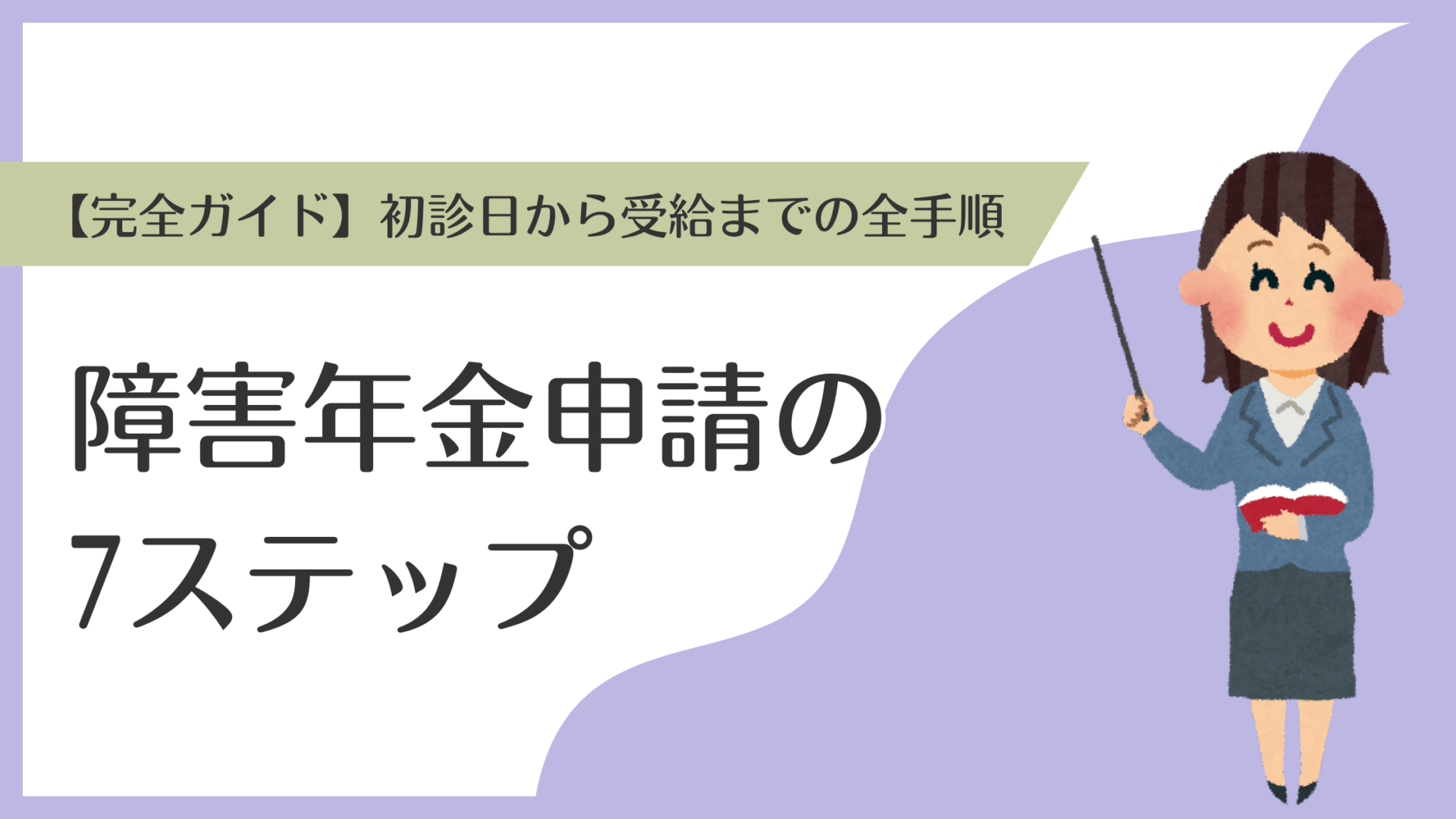
【完全ガイド】障害年金申請の7ステップ|初診日から受給までの全手順
はじめに|障害年金はあなたの生活を支える大切な制度です
何から始めたらいいか分からない…

障害年金の手続きは、たくさんの書類を準備する必要があり、とても複雑です。精神疾患を抱えながら、一人で進めるのは心身ともに大きな負担がかかるかもしれません。
しかし、障害年金はあなたの生活を経済的に支え、治療に専念するための大切な制度です。この制度を知らないまま諦めてしまうのは、あまりにももったいないことです。
この記事を読めば、複雑な手続きが7つのステップで丸わかり。申請のプロである社労士が、受給までの具体的な道筋を丁寧に解説します。
最後まで読めば、手続きの流れや必要な書類、そして「ここを抑えれば成功しやすい」という具体的なコツが分かります。ぜひ、この記事を保存して、ご自身のペースで一つずつ確認してみてくださいね。
ステップ1:障害年金で最も重要な『初診日』の特定
障害年金の請求は、すべて「初診日」(障害の原因となった病気で、初めて医師の診察を受けた日)から始まります。
精神疾患の場合、以下のような日が初診日となります。
- 初めて精神科や心療内科を受診した日
- 不眠症などで内科を受診するなど、精神疾患を疑わせる症状で初めて受診した日
途中で病院が変わったとしても、同じ病気や関連性の高い病気であれば、一番最初に受診した日が初診日です。初診日がわからない場合は、ご自身の記憶やご家族の協力を得て、できるだけ正確に思い出しましょう。
具体的な日にちが分からなくても、初診の医療機関名とだいたいの時期(例:平成○年夏頃)だけでも思い出しておくと、次のステップに進みやすくなります。
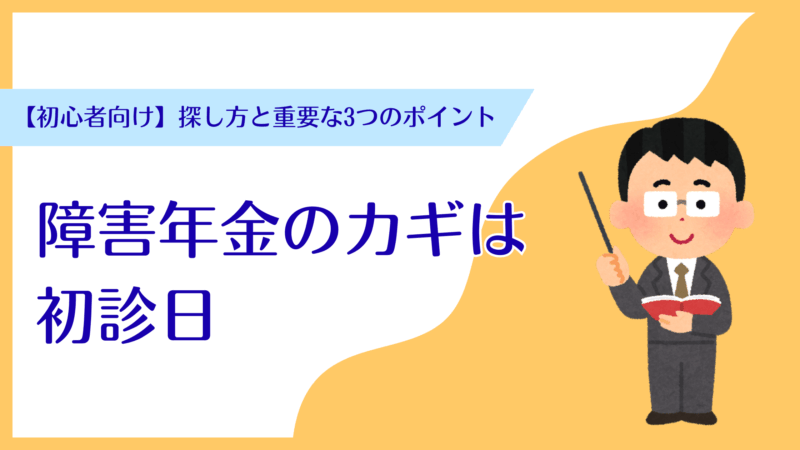
ステップ2:申請の第一歩:保険料の納付状況を確認
初診日が分かったら、その時点で保険料の納付状況を確認します。
以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 初診日の前日時点で、年金加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納めている(免除期間も含む)。
- 初診日の前日時点で、直近1年間に保険料の滞納がない。
この要件を満たしていないと、そもそも申請ができません。年金事務所や市区町村役場で確認できます。初診日の候補日が複数ある場合は、それぞれの日の納付状況を確認しておきましょう。
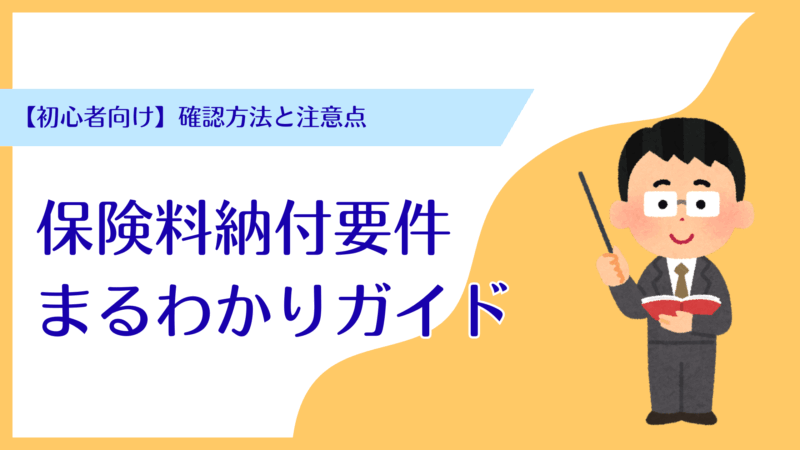
ステップ3:初診日証明でつまずかないための3つの注意点
初診日を証明する「受診状況等証明書」を、初診の医療機関で作成してもらいます。
初診日証明でつまずかないための3つの注意点
- 病院のカルテ保存期間は原則5年です。5年以上前の場合は書類作成が難しいことも。
- 初診日証明が不要なケースもあります。先天性の知的障害や、初診から同じ病院に通っている場合などです。
- すでにカルテが破棄されていて受診状況等証明書が取得できない場合でも、他の病院のカルテや第三者証明などを使って初診日を証明できることがあります。この場合は諦めずに、年金事務所や専門家にご相談ください。
ステップ4:最重要!『診断書』の依頼のコツ
障害年金専用の診断書を主治医に作成してもらいます。この診断書は、審査において最も重要な書類です。
正しい病状が反映された診断書を作成してもらうコツ
- 「障害認定日」での病状を診断書に書いてもらうことが基本です。障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日のことです。
- 日常生活や仕事でどんな支障があるか、いつもの診察では伝えていないことを、具体的に主治医に伝えましょう。
- 朝起きてから夜寝るまでの生活を振り返り、困っていることやできないことをあらかじめメモにまとめておくと、主治医にスムーズに伝えられます。
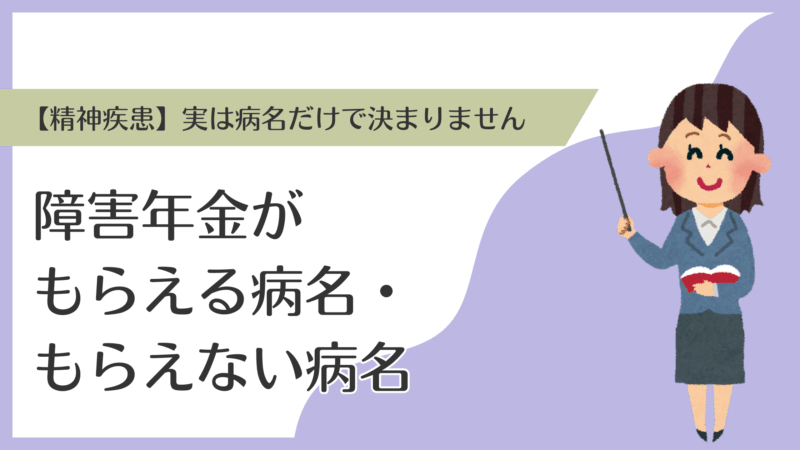
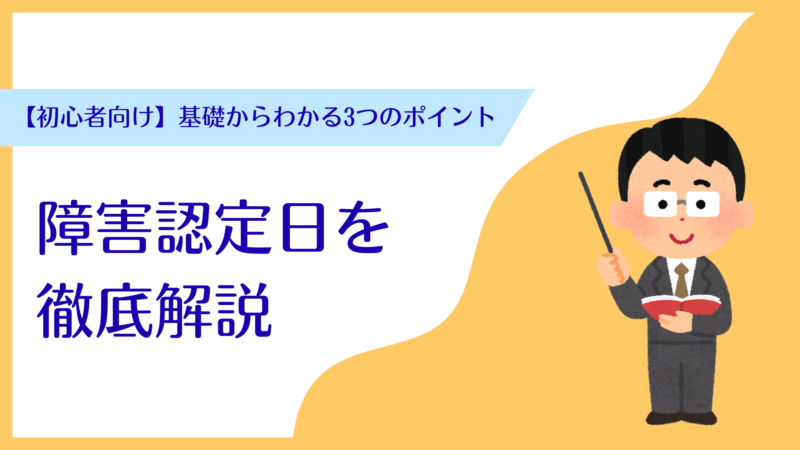
ステップ5:「病歴・就労状況等申立書」を作成する
この書類は、あなたの病気の発症から現在までの経過や、日常生活・仕事の状況をご自身の言葉で伝える、唯一の書類です。診断書だけでは伝わらない「つらさ」や「具体的な困難」を、審査官に直接訴えることができます。
障害年金の審査は、【あなた自身】ではなく、【提出された書類】によって行われます。
また、申立書を読むのは人間です。審査官があなたの状況を正確にイメージできるよう、簡潔に、分かりやすく、そして丁寧に書くことを意識しましょう。
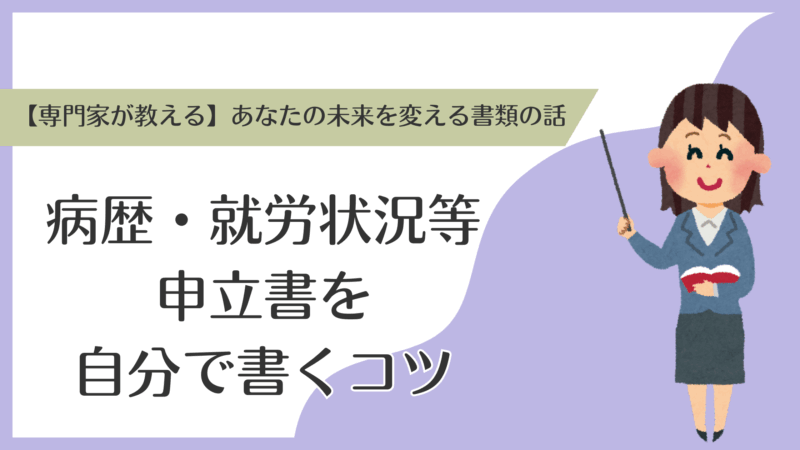
ステップ6:その他の必要書類を揃える
診断書や申立書のほかにも、通帳のコピーなど様々な書類が必要です。漏れがないよう、年金事務所で受け取るチェックリストを使って慎重に準備を進めましょう。
以前は住民票や戸籍謄本を自分で用意する必要がありましたが、現在はマイナンバーを使うことで、年金事務所側で書類を準備できるケースもあります。事前に確認しておくと、手続きがスムーズになります。
すべての書類が揃ったら、提出する前に必ず一度見直すことをお勧めします。
障害年金の提出書類一覧|日本年金機構ステップ7:年金事務所へ提出する
全ての書類が揃ったら、年金事務所などに提出して申請完了です。
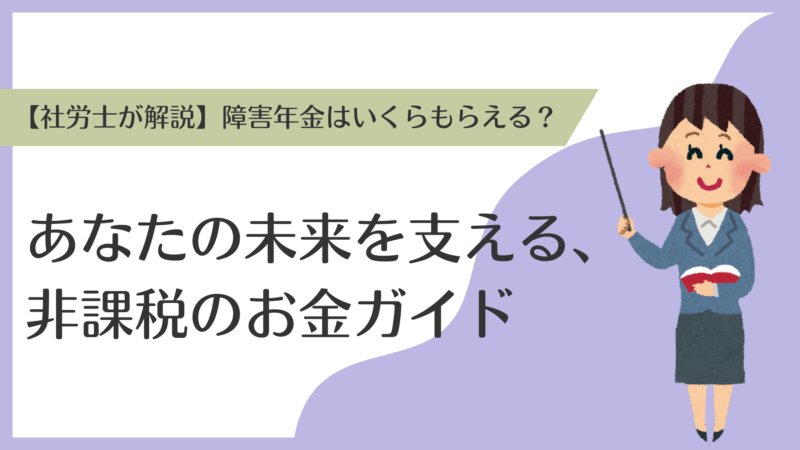
申請した後はどうなる?
提出後は、日本年金機構で審査が行われます。審査には通常3か月程度かかります。
- 審査が通った場合:「年金証書」と「決定通知書」が届きます。その後、年金が銀行口座に振り込まれます。
- 審査が通らなかった場合:「不支給決定通知書」が届きます。不服がある場合は、「審査請求」という不服申し立てをすることができます。
自分ひとりで申請できる?
もちろん可能です。
しかし、医療機関とのやりとりでストレスを抱えたり、「病歴・就労状況等申立書」を作成する際に、過去のつらい経験を思い出すことが大きな負担となる方も少なくありません。
また、特に注意していただきたいのが、障害年金申請は「一発勝負」と言われる点です。一度提出された書類は、不支給であったとしても保管され、次に申請する際の審査で参考にされます。そのため、初回の申請で事実と異なる書類を提出してしまうと、将来の申請で不利になる可能性があります。
さらに、事後重症請求や遡及請求では、申請が1ヶ月遅れるごとに、受け取れる年金額が1ヶ月分少なくなってしまいます。このことを考慮すると、専門家に支払う費用があったとしても、結果的に依頼したほうが、受け取れる年金の総額が多くなるケースも少なくありません。
最後に|不安な時は専門家にご相談ください
障害年金の申請手続きは、人それぞれ異なる難しさがあります。

自分の場合はどうなんだろう?
一人でやり遂げる自信がない…

そう感じたときは、どうか一人で不安を抱え込まないでくださいね。
私たちは、あなたのつらい状況に心から寄り添い、不安な気持ちを和らげるお手伝いをします。障害年金申請は、誰一人として同じケースはありません。専門の社労士があなたの状況を丁寧に伺い、受給までの最適な道筋を一緒に探します。
障害年金の請求手続き|日本年金機構